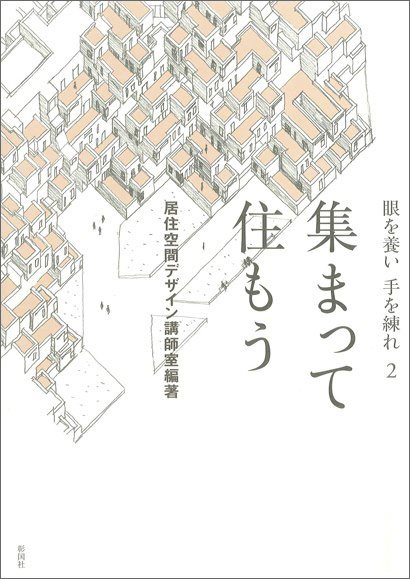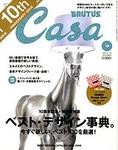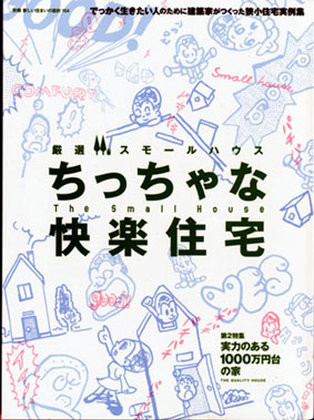�͎}�ɂ͗������˂��͗t���܂��킸���Ɏc���Ă��ĉ������猩��ƒ��̂悤�Ɍ����Ă��܂����Ƃ����Ȃ��Ȃ�����ǂ����̉e�͎O�Ƃ����������B�T�d�ɃY�[�����Ă݂���X�Y���Ƃ͈Ⴄ�X�Y����̒��B���Y�Ƃ͈Ⴄ���ȁB�悭���ꂽ�V�h���������̊������B�d����ɒʂ��̂��܂��y���B

[bigdog house]�̒ʂ�ɐ�K�Ⴓ��̏Z��ł����B [doghouse]�̒ʂ�ɂ���̏Z����������炱���2�g�ڂ̊���Ƃ������ƂɂȂ�B50m���炢�̋����ŃL�b�`���̑�����ڎ��ł���߂����B�����Ƌ߂��ɂ͒Ŗ����v����{�e�h��������邩�猚�z�Ɨ��̍����E�G�Ƃ������ƂɂȂ�B�n�E�X���[�J�[�̉Ƃ����Ȃ��͂Ȃ�������5.4m�̌�Ղ̖ڂȂ̂Ƒ����̉ƂɎ��������̂ŊX�̕��͋C�͈����Ȃ��B������������B�̂ǂ����B���̏Z��̌���ė��͋��Z��ԃR�[�X�̋����q��������ł͂܂�����Ă��Ȃ��B

�~�̋��̗��B�哿���ڌ��@���ʌ��J�ƕ��Ԃ�����̖ڋʂ͎�t�B�Ȃ��ł����s���������ق̐��a300�N���ʒ�͌����ł����B������킩��₷�����J�Ŏ�t�̉��[�������������܂łɂȂ��킩�����悤�Ɏv���܂��B��͂��t���Ō�܂Œ��킵�����Ă���B59�C�̌����`���ꂽ�u�S���}�v�͖����܂܂ɐ����Ă݂܂�����4�C�������ˁB���[�����X�ȁu�������ϐ}�v�ł͎�t���ǂꂩ�킩�����悤�ȋC�����܂����B��i�̎ʐ^�͎B��Ȃ��̂Œ[���ȑ������ʂ��Ă̋��s���]�B

�~�̋��̗��B�傫�Ȑ��ł͌����Ȃ���Casa�̓��W�����ɗ������B�n�����̂��ł��a�v�B�̒��߂��͋������̓`���̒��ł��������ɐ��܂��v�V�BCasa�Ȃ�ł͂̍ŐV���Ȃ̂��Ƃ͎v������ǂ������ł͂ƒm�荇���̋��s�ʂɂ�����������B��̂ɑ̌������Ƃ���A���N�O�ɗ����Ƃ���A�l�b�g�ŒT�蓖�Ă��Ƃ�������荬�����Ė{���͑�D���ȃX�^���v�����[�ɂȂ炩�����Ƃ���͐����̏��ȁB�ʐ^�͘a�v�B�u�O�v��2�K�B�v�͉�������B�J�E���^�[�z�ɔ��삪������B�T�b�V������J�E���^�[����������ĉ˂���ꂽ���V�̌����������Ԃ��h���Ă��ĊO����u�O�i�����j�̑сv�Ƃ��ăA�N�Z���g�ɂȂ��Ă���B������͎��̂悤�ɍׂ���̒O�������Ă���B�a�v�B�Ƃ͎v���Ȃ��s����Ȑڋq�̂������Ō��z�ɂ���S���s���Ă��܂������A���قɂł����܂�Ȃ�����܂Ƃ��Ȓ��߂��͏��Ȃ��Ƃ����}�[�P�b�g�̓ǂ݂͓������Ă���B

�~�̋��̗��B�����3���Ԃ͎n�܂�̏�����Ђƒ��߂̐����@�ɏd�X�O��̒�B�߂��̋T���̂̌����Ă���{�ɂ����ł���^�̐��E�̒��ł̌^�j�肪�h���I���B������Ђ́u�H���̒�v�i���j�Ƃ̍���j�Ɏʎ��I�ȋT�̒�����u�����͎̂O��Ȃ̂��낤�B�ʐ^�́u�����̒�v�̂��C�ɓ���V���b�g�B���������O�悪�D�����B

�~�̋��̗��B���Ă��Ȃ��f�r���̂����Ƃ������̂��Ƃ͎v���̂�����ǁA���Ԃɋ���������Ȃ������l�Ȃ̂�����ƌ����Ă��邤���ɁA�قƂ�ǂ̎��Ԃ��\��Ŗ��܂��Ă������B�\��̒[���͑哿���ڌ��@�̓��ʌ��J�ŕ������������Ă���v�������Ă��肬�肷�ׂ肱�B���i�͋����ɑ݂��o����Ă���i���Ȃǂ�����ׂ��Ƃ���Ŋς�̂��悩���������킹�Ă��̕��тɐ�Z����̌��ł����̂����n�������B��G�̋�͔��i�v�I�Ɏ��̂����������Ⴆ��200�N��ɂ����̋�Ԃ͂ǂ̂悤�Ɋς��Ă���̂��낤���ƗI�v�̎��̗���ɂ��z�����悹���B�哿���ō��킹�Ĕq�ςł����̂͗����@�A���ˉ@�A���@�A�����@�B�哿���Ƃ��������ȉF���ɂ��ꂼ��̌�����߂₩�ɑ��݂��Ă���̂������B�Ō�ɖK�ꂽ�����@�̒�͏d�X�O��B�ʐ^�����ˉ@�B�l�����������G�ɂȂ�B

���j���ɂ͑҂����킹�����ĉ���O�̃M�����Ԃɍs���Ă��܂����B�G���x�[�^�[�̔������܂��J���Ȃ��Ă���Ƌx�݂ł��邱�ƂɋC�Â����B�߂���21_21�ł́u�f�U�C���̉�U�W�v�͂��낤���Ƃ����ւ̗�B�M�����Ԃ̂��łɊ�낤�Ǝv�������x�������̂ł����ɒ��߂��B�T���g���[���p�ق͋x�݁B��͖��z�\�Ԃ́u�������v�Ɍ��߂Ă������疳�ʂȍs���͔������������̂���������������߂���͔̂����邱�Ƃɂ��āu��V���Y�W�v�̊O���O�ֈړ����C�܂���X�����̎n�܂�B���^���E���́u�i���W�����E�p�C�N�W�v��90�N��ȍ~�̌㔼�̕��B�����A�L�A���[�[�t�E�{�C�X�Ȃǂ����ĉ������������B�����̃R���[�e�͎ʐ^�ɎB�肽�������Ȃ��B�p���^�C�g�������Ĕ�����stuffed�Ȃ̂��w�K�B�l�߂��̗����Ɠ�������Ȃ���(��)�B�ʐ^�͓ې�̔����ł͂Ȃ������B���ʂ̐��D�����B