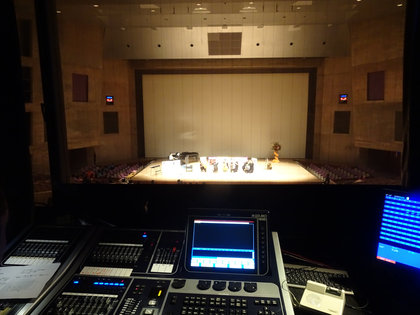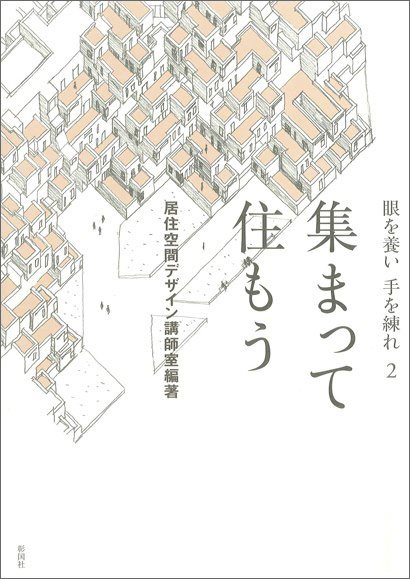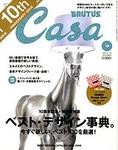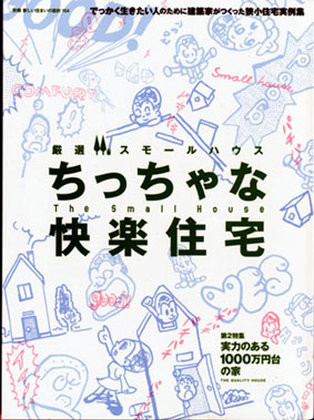新宿御苑菊花壇展つづき。ランドスケープとしての菊という観点からは池の端に設えられた黄色い島が一番印象的かな。

新宿御苑も秋。さまざまな菊が仕立て上げられていました。これは「大作り」。一株だそうです。


石垣島4。毎年石垣島に通っている友人が教えてくれたのが「ひとし石敢當店」。ネットで調べると予約が取りにくい人気店のようっだしそもそも夜はみんなで食事する店が決まっているのでほとんど諦めていたのだが「宮良殿内」の近くだったので見学後にできた自由時間の隙間を突いて開店の5時にトライ。案の定予約満席で30分以内オーダー1回という条件でなんとか入店。石垣牛握り、マグロ握りなどに満足。やってみるものですね。超人気店をとりあえず体験する手としてほかでも使えるかも。「石敢當」は沖縄で街角によく刻まれている魔除けの文字。魚は近くの公設市場での写真。こういう南国の魚もおいしいことは伊礼さんに習って経験済み。

東京都写真美術館:杉本博司 ロスト・ヒューマン。多岐にわたる膨大なコレクションを主体に展開される現代文明のエピタフ。33編の展示には1つを除いて「今日 世界は死んだ もしかすると昨日かもしれない」という寸分違わぬ言葉で始まる肉筆が添えられていて、浅田彰、磯崎新、南條史生など注意深く選定された人たちが代筆している。写真という表現の枠を大きく超えたモノの迫力に圧倒される。けれども写真のみの[廃墟劇場] [仏の海]シリーズに写し込められた意志の密度も尋常ではない。どうでもいいことだが、ラブドールの言葉だけ女言葉で綴られているのも杉本のこだわりか。

石垣島3。白保集落。「ンマガミチ」のこれも「ウタキ」かな。これは集落内に散見される聖なる場で直交する「カンヌミチ」の突き当りの集落はずれには鬱蒼とした森に護られた「ウタキ」がある。

かれこれ20年来の縁になる陶芸家の高鶴元さん。1985年にお招きいただいた福岡の登り窯建屋焼失後の初めての東京での個展。衝撃の陰を微塵も見せないどころはすごい。元気いっぱいの「パンプキンシリーズ」や私のお気に入りの「鳥付き花瓶」にはさすがに手がだせなかったけれども今年もぐい呑みを入手。去年の丸に今年の六角。