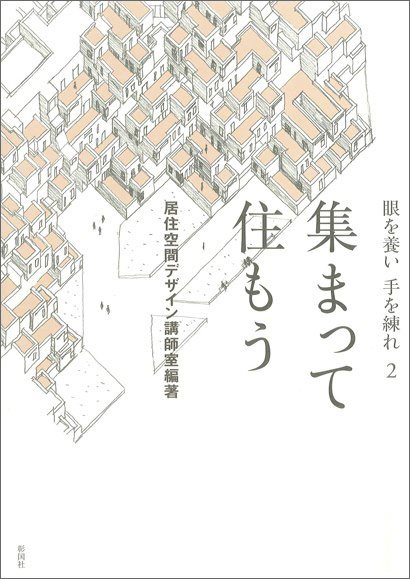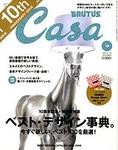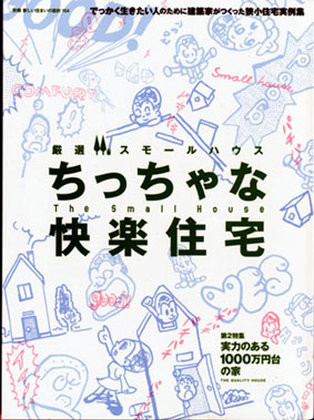稔り多い源兵衛川辺歩きには鰻重も付いているのがさらにうれしい。富士山の伏流水で鰻を育てているから美味しいのだそうだ。今回は超有名な「桜家」ではなく「うなよし」を選んだ。白焼きを含め納得の味だったが団体観光客を受け入れる、昼は酒は出さない、という経営方針が私たちには合わない(笑)。地元の人が贔屓にするような鰻に巡り合うには時間がかかるのだろう。

カワセミは小さくてあまり動かないから見つけるのはたいへんなのだが人が集まって息を止めているところには必ずいる。そっと集団に混ざりこんでカメラを同じ向きに構えていてコツコツと音が聞こえる方を見上げたらコゲラがいた。小ぶりのキツツキだ。これは伊豆高原で一度捉えたことがある。

シロハラに出会って喜んでいる矢先に長大な望遠レンズをかまえる「鳥おじさん」のひとりに行き当たった。もっとめずらしいのがいるよと指さしてくれてやっとみつけたのがトラツグミ。これは初めてだ。毎日通って朝から晩までいるのだそうでいろいろと詳しいわけだ。こういう触れ合いも街歩きの楽しみの一つだが男は不器用なのでちょっとした助けがないと素直になりにくい(笑)。

興味深く鳥を眺めているうちに名前のわかる鳥の種類が少しずつ増えてきた。普段の生活領域では出会う鳥の種類はかなり限られているのだが三島あたりまで足を伸ばすと様子は違ってくる。源兵衛川のシロハラを直ちに同定できた納得のつぶやきを聴いてもらえたのはうれしかった。

源兵衛川にカワセミがいるということはそこに魚棲むということ。だから鷺の類も歩きながら時々嘴を流れに刺している。こんなに真っ白だと水面下の魚たちに察知され易いのではと思うのだがそういうものではないのだろう。ちなみに脚の水に浸る部分は鮮やかな黄色だ。

5回目のカワセミとの出会い。すっかり鳥に馴染んできているせいか源兵衛川でもカワセミに出会った。しかもオスメス2羽。「鳥おじさん」によればオスとメスは流れの上手下手に分かれて棲んでいて川沿いに行ったり来たりしながら徐々に近づいていて、もうすぐゴールインだろうとのこと。この個体はオス。