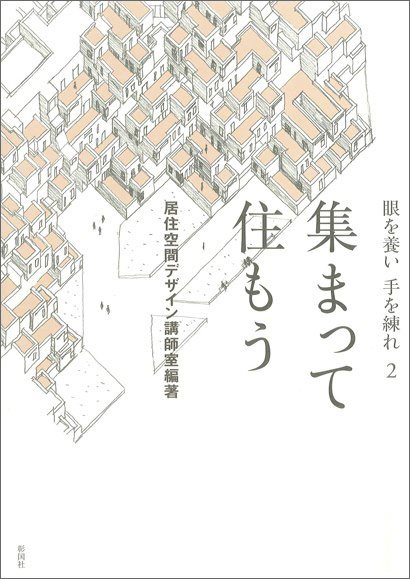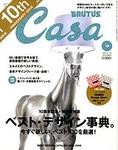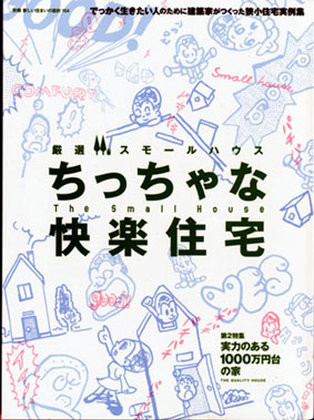ボストンの醸造家Paul Sylvaさんのご縁で1995年8月に出会った陶芸家の高鶴元さん。ボストン郊外のTopsfieldが本拠地で福岡にも登り窯があります。東京のデパートでの個展には毎年顔だけは出していたのですが、今年は手頃な価格の作品のなかにかなり惹かれるぐい呑みがあって、思い切ってゲット。ニューイングランドならではの独特な赤です。裏を見ると野球のボールの跡があるユーモラスな作品です。ボストン・レッドソックスの誰だかが打った球だそう。桐箱に仕舞っておいてはつまらないのでお酒をそそいでみると20年の想い出も交錯して何とも言えない風合いでした。

Amazonから届いたおすすめメールにびっくり。私の趣向をあまりにも正確に捉えているのです。こわいなあ。以下に列挙:「日本精神史(上)」長谷川 宏、「Mary Travers: A Woman's Words 」Mary Travers、「現代建築に関する16章」五十嵐太郎、「わたしのとっておきワインのつまみ」サルボ恭子、「日本デザイン論」伊藤ていじ、「南方熊楠―森羅万象に挑んだ巨人」中瀬喜陽、「地球の歩き方 キューバ&カリブの島々2015 」地球の歩き方編集室編 。 写真は通勤途上の晩秋。

すらっと伸びた葱のような太くて柔らかい茎の先のまだ開く前のアマリリス。ハナミドリからちょっと苦労して持ち帰りました。ヒガンバナ科ヒッペアストルム属Amaryllidaceae Hippeastrum。分類学上はラン科アヤメ科などと共にアスパラガス目。分類学の世界も面白そうだなあ。写真はスマホの勝ち。ズームできることを知らずに使っていたのだから笑ってしまいます。
 オールアバウト
オールアバウトに高円寺の住宅[enne]がアップされています。生活がスタートしてからの写真も使われています。写真はまだまだ元気なヒペリカム。

富士山に纏わりつく雲、霞、雪煙。刻々と変化する様は見ていて飽きません。

旧くからの仕事仲間との師走の吉祥寺鼎飲。今年はかなり趣向を変えて「破」にLPの聴けるダイニングバー
[quattro labo]を選びました。スピーカーの前のカウンター席を予約。店のターゲットになっている若者たちは旧いLPに興味がないのかほとんどリクエストをしないのでターンテーブルをほぼ独占できるのです。ところが平日は勝手が違っていました。Rubber Soulの次にByrdsをリクエストしたあたりでDJが登場。LP単位ではなく一曲一曲目の前の私たちに合わせて実に気の利いた選曲を展開してくれたのです。New MorningからThe Man In Me、The BandはMoondog Matineeからなど渋い。Area Code 615、Tony Kosinecまで登場して時間はアッという間に過ぎて行きました。自分で回せたら最高だろうなあ。で「急」はお決まりのSometime。音楽に浸り込んだ流れなのでたいして期待していなかったのにこの日に限って音楽が異色。オーソドックスなジャズではなく西洋周縁音楽の坩堝といった感じのクインテット
Tokyo Groove Allianceだったのです。解説によれば守備範囲はjazz, funk, Arabic, aboriginal, European renaissance and rockだそう。アラブの香りを漂わせる複合音は刺激的でした。メンバーの中の唯一の日本人太田惠資はどこかで見たことがあるなあ。

コンデジ30倍望遠ファインダー付きだから撮れる鳥。かわいい。