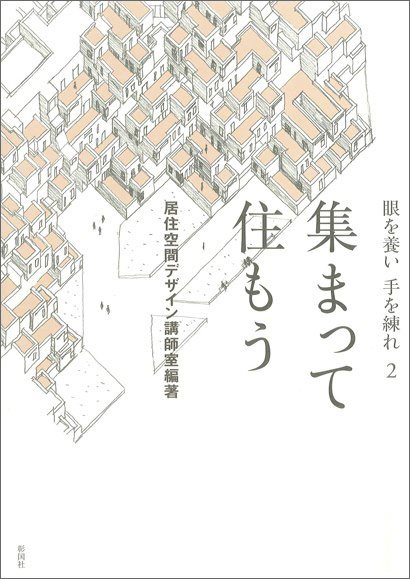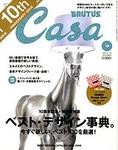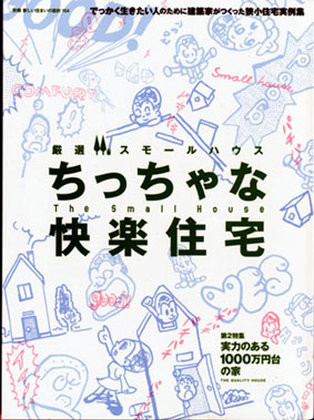最近は大好きな虎だってテレビ観戦は皆無だしテレビでサッカーなんてこともないのだが、4年ごとに俄かサッカーファンになる。録画しておいて情報をシャットアウトして帰って即寝て早起きして観る。薄氷のトーナメント進出、よかった。今日はこれからゼミ旅行。京都に向かっている。



勝沼逍遥。ディナーは
「ミルプランタン」を選んだ。設計したワイナリーがオープンする時にお世話になったシェフの店だ。設計監理の仕事の前に事業策定の仕事を受注していて、その段階で営業、宣伝、企画、醸造、資材などメルシャンの多様な社員からなるチームをつくってもらい、私もその一員となってチームとして会社に事業計画案を答申した。ワイナリー事業のすべてを考えるわけだからその中のレストランのメニューにまで首をつっこんだ。ほとんどが醸造の現場の人たちから教わったことがヒントになっているのだが、例えば赤ワイン醸造の時に使う卵の白身のあまりの黄身を使ったカヌレ、葡萄の若葉のフライ、間引かれた青い葡萄の実を絞ってつくるドレッシング、まわりの山にたくさん棲息する鹿料理などなど。採用されたものは実はないのだけれど、その議論の過程の中で「土地の恵み」が大切であることを学んだ。そう言えばワインそのものが「土地の恵み=テロワール」だけから生まれる稀有な酒だ。期待通り「ミルプランタン」のメニューも土地の旬の素材の持ち味を巧みに引き出していた。写真は土地で獲れた野菜をキャセロールで蒸し焼きにしたもの。青紫色のブロッコリーを使うことで見事な彩りの一皿にしたところは技あり。ワインは赤にしたかったのでボルドーの手頃なものにした。日が落ちた後の山ぎわの青が美しかった。駅で燕のつがいに見送られて列車に乗った。幸せでいっぱいでもうワインはほとんど要らなかった。



勝沼逍遥。勝沼は緩やかな傾斜で水はけがよく周囲の山から流れ落ちてくる水が豊富だ。大きな日川と並行しておそらく用水路が起源だと思われる水量の多い小さな川が幾条もある。そんな川の一つに面した気持ちの良いテラスのあるワイナリーが「勝沼醸造」。川の向こうに垣根式の葡萄畑がひろがっているからついワインも進んでしまう。有料試飲8種のうち6種が甲州なのがうれしい。赤は山葡萄系の小公子と私が苦手なマスカット・ベーリーA。白の甲州に次ぐ赤の日本在来種の成長が望まれる。帰りの車内用に小公子をゲット。ディナーまでにはまだ時間があるのでワイナリーもう一軒と思った手の先にいい印刷物があった。勝沼界隈で食・酒・宿泊・アートを楽しめる古民家を集めた「山梨古民家倶楽部」の冊子。勝沼醸造、原茂、丸藤に並んで「くらむぼんワイン」が載っている。このワイナリーの変な名には好印象を持っていなかったのだが、冊子に宮沢賢治の童話に由来するとあって、調べてみたら
童話「やまなし」の動画に行き当たった。清流に棲む蟹がつぶやく言葉が「くらむぼん」。カムパネルラ、ザネリ、宮沢賢治の得意技だ。蟹は泳いでいる魚が翡翠に捕食される瞬間を目にする。動画でのこの瞬間は印象的だ。「自然環境と人間の共存を目指すワイナリー」だからこそのネーミングなのだと知れば行かないわけにはいかない。訪ねてわかった、2014年までは「山梨ワイン」だったから耳慣れなかったのだ。新参ではなく1913年開業。リリースされたばかりの蟹のエチケットの甲州と天然酵母無濾過の甲州を試飲して後者を選んだ。靴を脱ぎ座敷で寛いだ時間もよかった。勝沼は着実に成長している。