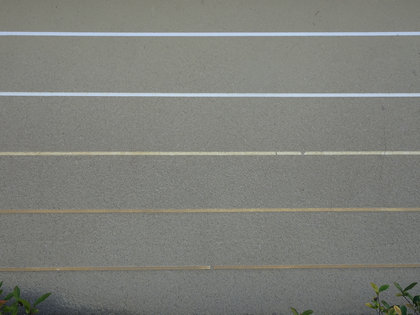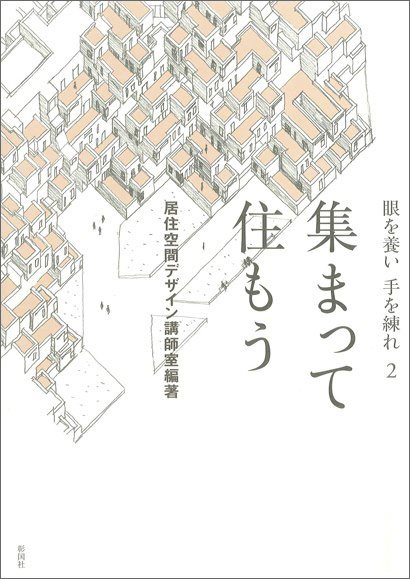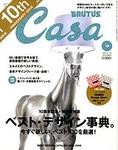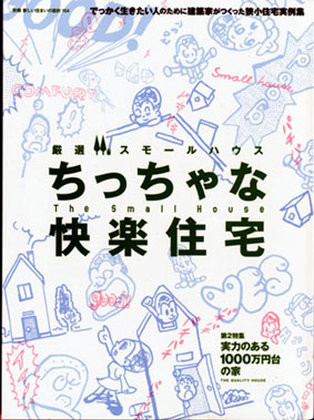�~�̋��̗��B�����3���Ԃ͎n�܂�̏�����Ђƒ��߂̐����@�ɏd�X�O��̒�B�߂��̋T���̂̌����Ă���{�ɂ����ł���^�̐��E�̒��ł̌^�j�肪�h���I���B������Ђ́u�H���̒�v�i���j�Ƃ̍���j�Ɏʎ��I�ȋT�̒�����u�����͎̂O��Ȃ̂��낤�B�ʐ^�́u�����̒�v�̂��C�ɓ���V���b�g�B���������O�悪�D�����B
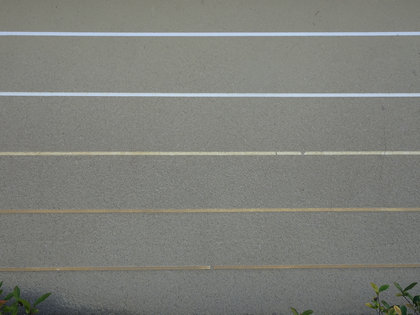
�~�̋��̗��B�����@�Ŏ�t�̌{���ς����ƍ��䎛�Ɍ���������Ő��ɕ����Ă����B�X�}�z�Ȃ��ł�������Ƃ������M���ז������ċC�Â��̂Ɏ��Ԃ����������B�L�̂悤�ɑ��z�̈ʒu�ŕ��ʂf���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��̂��B���̓��̒��ɂ͈��]�v�ɓ쉺����ԈႢ���������Ă��Č��Lj����19.3km���������B��蓹�����邱�Ƃŗ\�����ʊX���ł����ƈԂ߂Ă���������ȍ~�̓X�}�z���d�p����悤�ɂ����B���̕������o�����������_�̌��m�������Ō����������̌ܐ��O���f�[�V�����B���s�炵���ʎa�V�Ȕ��z�ɓ��Ă�ꂽ�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����낤�B�������^�C�g�����p���Ȃ̂Ōܐ����̉p����O�O����staff notation�Ȃ̂��w�K�B�p�P����ӊO�ɒm��Ȃ��Ȃ��B

�~�̋��̗��B���s�͐삪�����������X���ō�̗ނ��������邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��B����◓���Ȃǂɔ������ɂ��������Ă����͏��蕨���ȂƋ^���Ă݂�������邪���̍��L�͏��蕨���B�������낢�B��t�́u��~�Y�{�}�v�����ʌ��J����Ă��錚�m�������@���獂�䎛�Ɍ�����������ł̈ꖇ�B

���ꂽ���ɂ͒����������₩���B�~�͂��������̎��X�̗t�������Ă��邩��ނ�̋�������ɂƂ܂�Ղ�����ǁA�ׂ����������̕\��܂ő����邱�Ƃ��ł���̂͂قڋ��R���B�����J�͂��킢���B�V�h���������B

�~�̋��̗��B�ȑO�ɂ�����Ə������v���o�[��
���哰�ցB�������O����m��Ȃ������̂����N����Ɋm�F�ɏo�����Ĉȍ~�́A�����鉳���̎c�������߂��āA���������Ă����B�E�ъ�����[���̂���������͂�₵�����Y���Ă����B�O���l�ɂ͐l�C���Ȃ��̂������̂����������Ă������炩������Ȃ��B�u����窠�v�Ƃ������O�̂Ƃ��荂�፷�̑���������킢�[���B�Â����̒��̎��Ђ��̉����傫�������B�u�m�s�v�u�Y���v�Ƃ����Ăі������邱�Ƃ͏��߂Ēm�����B��q�̊J�����c�����ɘȂޘV�L�̎ʐ^����ԕ��͋C��\���Ă��邩�ȁB

�����[�N�V���b�v�͈���6�����d���n�߁B�����낢��Ƃ����b�ɂȂ��Ă��錚�݉�Ђ̒C���N��̎�@�������Ă��Ă��ꂽ�B�N�₩�ȐԂ̖{���߂̃f�U�C���͖�V���Y����B�I�����s�b�N�E�G���u�����̊v�V�I�f�U�C���ʼn₩�Ɏ��̐l�ƂȂ�����V����ƒC�̉����q�����̂̓��[�N�V���b�v�Ƀf�X�N��u���Ă��錚�z�Ƃ̓c粗j����B�c粂���Ƃ̏o��͓��吶�Y�H�w���f�U�C���R�[�X�̎������ꂳ��̏Љ�B���X�Ɍq�����Ă������͊y�����Ȃ��B

�J���c���U���Ă����2004�N������吶�Y�H�w�����Z�R�[�X�Ŕ�������悤�ɂȂ����B�J���c����k�R����Ƃ�1970�N�ɉ��l����ŏo�����1978�N�ɂ�3�l�Łu���[�N�V���b�v�v��ݗ�����i���t���������B���̖k�R�����Z�R�[�X�̋{�e�܂ɃQ�X�g�R�����ŗ��Ă����B47�N�ɂ��y�ԉi�����Ɋ����ʁB�ʐ^�͏d�X�O��̒���ςɍs�������s�E������Ђ̂������B