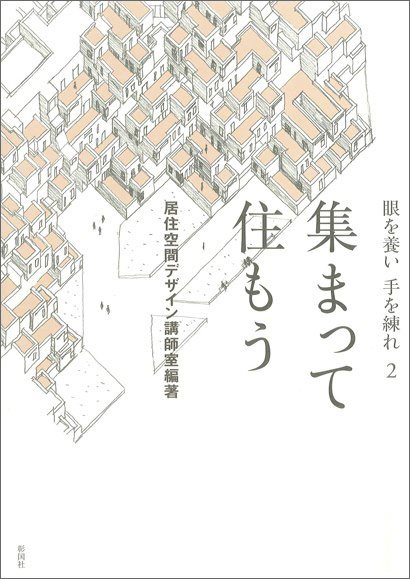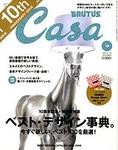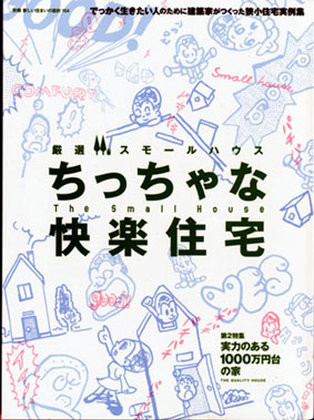8月の
house M「伝統文化対話シリーズ」の続編に参加させていただいた。草月流師範の大泉麗仁さんの「いけばなの空間とかたち」レクチュアが興味深かった。いけばなは空間とともに変化しているそうだ。余談だがこの夏にうっかり見入ってしまった「生け花ドラマ」のいけばなは草月流だそう。あれは私には手に負えないと思っていたが、身近で優しく説明を聴くと興味も涌く。中庭で菓子・茶をいただきながらの談も、1階に上がっての宴も、稔り多い時間だった。中庭での焚き木がうまく行かなかったのは残念。次回は私が火を熾すことになってしまったように記憶している。口は幸せのもと(笑)。石田敏明さん郡裕美さんとの再会もうれしい。室伏さんの縁、ありがとう。もとをたどれば居住だ。

初めての谷津干潟でセイタカシギに出会った。水辺の遊歩道を散歩している犬連れの女性と目が合ったので「鳥がいますよ」と声をかけたら「セイタカシギですね」と返って来た。愛称かと思っていたらどうも本名らしい。野鳥が生活に根付いているということかな。葛西海浜臨海公園の鴫がちょこちょこと歩き回っていたのに比べると動きが少ない。かわいい。じっと眺めているうちに陽が傾いてきて白いお腹が夕焼け色に染まったのが水面に映った。あとで写真を拡大すると折りたたまれた片脚が写っていたりする。ついでに写ってしまう水が清らかとは言い難いのは気になる。セイタカシギ背高鷸Himantopus himantopusチドリ目セイタカシギ科。英語はblack-winged stilt。

習志野の大学に15年も通っているのに足を向けたことのなかった谷津干潟に行った。手前にあるバラ園の前身である谷津遊園には小学校の時に行った記憶が微かにある。そう遠くはない本八幡に当時は住んでいたのだ。全体は朧げなのだが芝生の上で同級生だったかとも一緒にお弁当を食べている情景が鮮明だ。干潟となっているあたりは当時は遠浅の潮干狩りの浜だったはず。あっという間に遥か先まで埋め立ててしまったわけだ。このあたりにはほかにも「船橋ヘルスセンター」「ザウス」とか仇花のように散ってしまった施設があった。あの巨大スキー場はバブルだなあ。そんな荒っぽい都市環境だから対岸の埋め立て地のランドスケープは手放しでは愛でられないがそれでも秋晴れの一日の夕暮れ時は思ったとおりに美しかった。アオサギが小さく写っている。

日本の文化とは縁もゆかりもない異国の慣習がいつの間にか商業化されて少なくとも東京では恒例のイベントになってしまっている。大阪在住のいとこが仕事で上京した折に何十年振りかに再会することになったのがたまたま31日で、私と同じく好奇心旺盛で一回り以上若い彼が渋谷に行きたいというので、一緒にでかけた。ハチ公前交差点は仮装であふれていたが警察の警備も大掛かりで強引な規制を平然とやっていた。とりあえず戯れているだけだからみんな大人しく従っている。こんなことで満足している時勢ではないだろう。

grutto pass #15。行きつけの検査クリニックが近くなので用事があったついでに寄った。これでスタンプラリー完。エリアが7つに分かれていて達成はよほどの暇人でないと無理だから賞品が当たるに違いない。大昔「がきデカ」という漫画に載って脚光を浴びた「きょん」がいた囲いではエゾシカの背中にカラスが乗っかって遊ぶ姿を目撃したのだがカメラは間に合わなかった。キョン羌シカ科ホエジカ属Muntiacus reevesi。