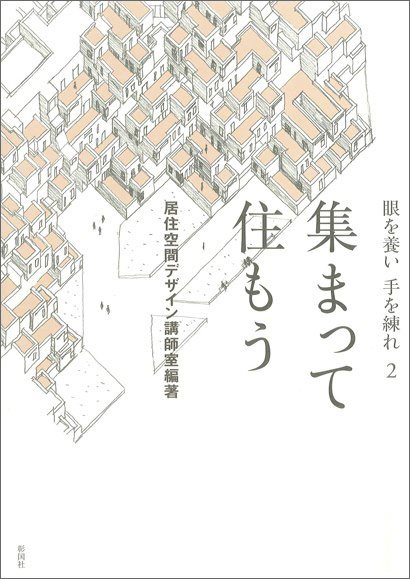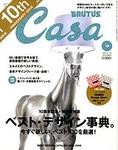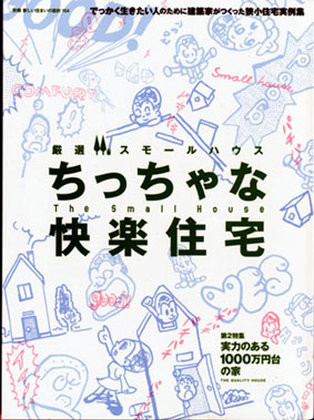日大生産工学部居住空間コースの年間最優秀課題作品を選ぶ第20回宮脇賞。ゲスト審査員は吉村靖孝さん。作品が質、量ともにアップしているのがうれしい。審査員総数は19人で恒例の中村好文さんの名司会もあって熱のこもった審査会になった。もう年寄りの部類に入る私は思うままに偏った発言で楽しませていただいた。最優秀賞「とまり木」(3年堀内さん)は確かに群を抜く秀作なのだが、主題と無関係に(私には)思える形態操作の鮮やかさが先行しているのが気になって、ふたことも言ってしまった。木下道郎賞は2年荻野さん。3×3×5mの枠に押し込もうとする課題の枠を打ち破る心意気が好き。授賞式に続く懇親会での建築家と学生のダイアローグが居住空間コースの真骨頂。講師陣の層の厚さが効いている。学生たちもそれぞれに楽しんでいる。今回は吉村さんの早稲田の学生さんも参加してくれて興味深い意見を拝聴させていただいた。片付けが始まってもなお議論さめやらぬの前でパチリの圖。

お気に入りの割烹に向かって木屋町通に上がろうと御池通を西に向かっている眼の向こうをアオサギがさっと過って街灯の細い横桟に留まった。京の冬の旅はこれで締めようかな。


京の冬の旅。せっかく来た旅先では新しい店を探したいものだと思いながらもついつい惹かれてしまう味の記憶も蔑ろにはできない。出汁へのこだわりを原点に定めた麩屋町の「ラディカルおでん」をまた味わえてよかった。ここは確かだ。「おにく」には唸る。

京の冬の旅。大原からの帰りの国際会館駅での乗り換えに時間があったのでぶらぶらした宝ヶ池畔で出会ったジョウビタキ♂。年末の保田から鳥の世界は続いている。

京の冬の旅。3度目の重森三玲庭園美術館。既成の枠には収まりきれない才能がなんとか庭の世界で開いたということなのだろう。三玲がつくろうとしていたという茶道も華道も庭も含めた総合芸術大学ができていたら建築も今とは違っていたかも。三玲を写真で表現するのは意外に難しい。


「正月」が明けた直ぐ後まだ「日常」に戻り切る少し前の京都に行ってきた。「のぞみ」が6日まで正月価格でどうにもならないのを除けば、宿泊料金は穏やかで土曜に限れば普段より安いくらいで、正月休みもほとんど終わっている。京都駅に昼前に着いて駅ビルの「和久傳」での青竹酒から始まるのは今年も同じ。コースの締めの黒鯛鮨までつまみになるところがうれしい。


「道の駅保田小学校」は小学校をリノベーションして道の駅とするコンペの成果。委員長は布野修司さん。北山さんたちのプログラムは宿泊、飲食、温泉、市場などの複合施設。北山さん担当のパートは2階建の教室棟南側に増築した「縁側」。1階では飲食店群のポルティコとなる屋外空間で2階は宿泊施設の中間領域となっている。中間領域は宿泊室の共用空間で室温調整機能を担っている。反射輻射面と吸熱蓄熱面が反転する手動パネルのアイデアがいい。寒い日だったけれど暑いと言っている人もいるくらいの効果だった。この中間領域を時間帯によって来館者に解放しているのもいいと思う。